地域雑誌「谷中 根津 千駄木」1号
/ 1984年10月15日(月曜日)発行
100円
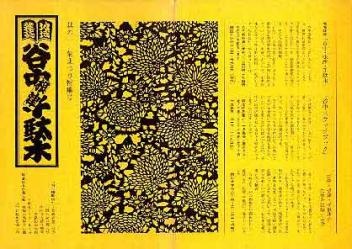
地域雑誌 谷中根津千駄木
その一 菊まつり特集号
”向う横町の”
笠森お仙子守唄
団子坂の菊人形
大円寺と瘡守稲荷
笠森お仙伝説
三崎坂イラストまっぷ
明治はるか菊人形
植梅の浅井さん他
文章に現れた菊人形
むこうよこちょのおいなりさんへ いっせんあげて
ちゃっとおがんでおせんの茶屋へ
こしをかけたらしぶ茶をだして
しぶ茶よこよこよこめでみたらば
こめのだんごか つちのだんごか おだんごだんご
このだんごをいぬにやろうか ねこにやろうか
とうとうとんびにさらわれた
笠森お仙に題を取ったこの歌は、昭和初期のころまで、東京を中心に関東・東北地方で広く歌われた。
笠森稲荷に願をかけるときは、まず土の団子を供え、願いが叶って願ほどきには、米の団子を供える慣わしだった。だから門前の茶店では、土と米と両方の団子を売り、茶屋の女たちは、「米のかえー、土のかえー」と声をかぎりに叫びたてていた。
団子坂とは地下鉄千代田線千駄木駅の出たところを本郷方面に上がってゆく坂である。古くからの道で汐見坂、千駄木坂、七面坂、菊見坂の別称もあるらしい。
団子坂の名は、団子茶屋があったからとの説もあるが、明治末にはもう一軒もなかった。急なためコロコロ団子のようにコケる人が続出したからとも、団子のよ うな小石があったとも。とにかく上り一町幅二間半と狭くて急で、しかもS字型に曲がって、上から来ると奈落の底に沈んでいくような心地がしたとか。
馬車や人力車で来てもたいてい、坂の上下で降りて歩き、そのための高下駄も用意されていた。なかには命しらずもいて、曲り角で車もろとも転がって大怪我を した話もある。そのショック除けに、S字の曲る角には木の柵がしてあったという。周りは森、下は田んぼ。今、ビルの立ち並ぶ坂からは想像もつかない眺めで ある。
この本郷台へ上る丘を千駄木山といった。坂上に森鴎外が、明治二十五年から大正十一年、死去するまで住んだ千朶山房があり、遠く品川の海を臨めるので、のち観潮楼と称した。今の区立鴎外記念本郷図書館である。
自雷也もがまも枯れたり団子坂(子規)
さて、いつのころからか染井、駒込から千駄木にかけては植木屋が多く、文化年間、巣鴨で菊人形をはじめ、それが大当りをとったのにあやかって、団子坂でも始まったのが安政三年(一八五六)という。
維新前の団子坂の貴重な資料として英人ロバート・フォーチュンの紀行文がある(『江戸と北京』一八六三)。
「この美しい土地は谷間にある。両側には木の茂った丘があり、峡谷から丘の際にかけて庭園や魚のいる池や茶屋がある。
・・・・この庭園で最も奇妙な眺めは、菊の花で作り上げた夫人の像【イミテーション・レディ】であった。そのために何千という花が用いられている」
初めて木戸銭(三文)を取って菊人形を見せたのは明治八年。これが大評判になって翌年には三十軒も店が出た。種半、植惣、植梅、植重、植浅、高木、薫風 園、花屋などが有名である。出し物は忠臣蔵、八犬伝、太閤記、曽我の仇討などの人気芝居がテーマ。首は人形師が人気俳優そっくりに作る。使うのは一度切り である。
人形の衣装の小菊はこの近辺では間に合わず、染井、巣鴨や王子あたりから取り寄せた。これを竹細工で編んだ胴に根つきのまま植えるが、ほぼ五日ごとに萎れ たのを取りかえるのと、水やりの作業で職人たちはクタクタだった。菊人形のほか、けんがいや大輪など、花壇菊もかざって見せていた。
明治十年ごろが一つのピークで、十五年ごろは団子坂が一手にひきうけ、二十年代が最盛期、日露戦争後はやや廃れ、明治四十二年、名古屋の黄花園が両国国技館に菊人形を開いたのに人気をさらわれ、四十五年、団子坂の菊人形は潰滅した。
団子坂下から谷中の方へ、柳通りと三崎の商店街を抜けて上がってゆく。すると左側、OBスタジオのクラシックなビルの隣りに大円寺はある。
高光山大円寺の創立は古く、天正十九年(一五九一)、家康が関東八ヵ国を秀吉から賜って、江戸に入城した翌年。その頃の江戸は字のごとく、葦がぼうぼうと生えた入江の沼地であった。
大円寺は大円院日授上人によってその年、神田加賀原に建立された。いまの医科歯科大のあたりである。もっとも上人が草庵を結び、日蓮像を安置したのは、それより以前の天文年間(一五三二〜五四)、いわゆる戦国の世のさなかである。
さて、徳川の世となって、江戸は首府になり、お城を中心に街づくりがすすめられると、神田は江戸の中心部で重要視され、神田にあった寺町は区画整理で郊外 に移された。天和二年(一六八二)のいわゆる「八百屋お七の火事」で類焼した大円寺は、上野寛永寺の清水門脇、今の清水坂(暗闇坂)の辺に移る。
さらに元禄十六年(一七〇三)の大地震と火事で、またまた大円寺は焼失。このとき現在地の谷中に移った。この火事で江戸の町の大半は倒壊、死者は四万と伝 えられる。このころ幕府の日蓮宗への弾圧が激しかったが、 大円寺は第六世日身上人が檀徒をまとめ、災難を乗り切っている。
そして大円寺に瘡守稲荷が遷座したのは享保十年(一七二五)五月十九日のこと。もともとは檀徒の白山の旗本、大前孫兵衛重職【しげもと】の邸にあった。彼 は自身、腫物【はれもの】に苦しみ、この病に霊験あらたかな摂津芥川(大阪府)の笠守様を、宝永年間に自邸に勧誘し、お祈りすると、たちまちにして癒っ た。その評判が江戸中に伝わり、人々が大前邸に押しかけて困るというので、大前氏が大円寺に移したものである。
それ以来、「谷中の瘡守様」は腫物(皮膚病)と腰から下の病に霊験あらたかというので、民間信仰の中でも特に参詣人が多かった。梅毒などに苦しむ吉原の女 郎たちも髪をしゃぐまに結い、歩いて急な三崎坂を下ってきた、とは「まつうら」酒店の松浦照子さんの記憶である。もっとも今は痔とかアトピーの平癒祈願が 多いそうだ
大円寺は紫陽花【あじさい】の美しい、しっとりとした寺である。が中に入ると本堂が二つ棟を合わせつながった不思議な形をしているのに気付く。右が薬王殿 で瘡守様を祀り、左は経王殿で祖師日蓮像を祀っている。つまり右は神式で左は仏式。こんなおもしろいスタイルの寺は東京広しといえどここだけである。これ は明治の神仏分離の危機を、瘡守稲荷(神)を薬王菩薩(仏)の形に変えて乗り切った。二十二世日★上人の苦心の表われである。
(インターネット版注 ★マークは言べんに甚の字です。パソコンではでないのでご勘弁を)
数々の工夫を凝らして錦絵を草創した鈴木春信と、彼のモデルで明和の美女と謳われた笠森お仙。これは春信の筆がたつのでお仙が有名になったのか、あまりにお仙が美しいので春信の絵が売れたのか、卵とニワトリみたいな関係にある。
この二人の碑が大円寺境内、本堂の向って右手に建てられたのは大正八年、春信の百五十回忌。春信の碑は笹川臨風お仙の碑は永井荷風の撰文によるもの。
笠森お仙はたしかに笠森稲荷の門前の茶屋に、江戸は明和のころいた美しい茶汲み女であるが、それは実は谷中の大円寺の瘡守稲荷ではなく、感応寺(いまの天 王寺)の子院福泉院にあった笠森稲荷なのだという。 三崎坂を上って菓子屋の角を左へ曲がり日暮里駅へ向かう途中右側に功徳林寺という寺があり、お仙のいた笠森稲荷があったのはここら辺り、大円寺の谷中瘡守 に対し、日暮里の笠森様という。
笠森お仙の美しさは、「ひとたび見れば人の足を駐【とど】む。再び見れば人腰を抜かす」(大田南畝)とまでいわれたぐらい。浅草観音奥山の楊子屋のいちょ う娘お藤と、天下の人気を二分したが、お藤が化粧の濃い人工的な美女であったのにくらべ、お仙は白粉に汚されることのないナチュラルな美女であった。
その天女が降り立ったような美しさを一目見ようと稲荷の門前はごった返し、お仙の姿は錦絵【プロマイド】、読み売り【しんぶん】のモデルとなり、手拭いに も染まり、和歌川柳にもうたわれ、ついにはお仙のような美人を生みたい親の願かけが始まる始末。 お仙が百姓娘だの、恋愛沙汰だの、怪死だのの巷説は、これに題材をとった芝居のフィクションである。有名な手まり唄は冊子の冒頭に掲げた。
本当のところ、お仙は茶屋鍵屋五兵衛の実の娘で、あんなにもてはやされたのに二〜三年で店から姿を消し、幕府お庭番の倉地政之助と結婚して久太郎ほか数人の子をなし、平和な一生を送っている。
しかし引退後もお仙は人の噂に上り、「とんだ茶釜が薬鑵缶に化ける」の言いまわしを流行らせた。お仙めあてに行ってみると、美女はいなくて、親父五兵衛の ハゲ頭しか見えなかったというわけ。引き際の見事さ、幸せな人妻ぶり、引退後の神格化という点で、明和の美女は、昭和の百恵ちゃんにそっくりだ。
春信とお仙の碑は場所こそ違え、感応寺と同じ日蓮宗の古刹大円寺に建っており、特にお仙の碑文はいかにも荷風らしい小粋なもの。
「女ならでは夜の明けぬ日の本の名物、五大州に知れ渡るもの、錦絵と吉原なり、笠森の茶屋かぎや阿仙、春信の錦絵に面影をとどめて百五十有余年、嬌名今に高し。今年都門の粋人春信が忌日を選びて、ここに阿仙の碑を建つ。時恰も大正己末夏鰹のうまひ頃」
三崎の地名の由来は古く鎌倉時代にさかのぼるという。
当時は不忍通りの低地は海で谷中、駒込、田端の三つの台地が岬となっていたことから、三崎の名が起こった。
三崎坂から団子坂へ、そして本郷へのルートは、五百年位前から開けた古道である。三崎坂はまたの名を首ふり坂。昔々どこの寺にか、首をふって歩くお坊様がいたからとか。
坂下のよみせ通りからへび道へとつながる通りには藍染川が流れ、びわ橋という橋がかかっていた。
今は文京区の柳通り商店街から、よみせ通りを渡って台東区のさんさき坂商店街に入る。
いわば谷中への入り口で、谷中散歩には日暮里駅からのルートも良いが、千代田線千駄木駅からのルートも便利。
商店街では「江戸のある町」のイメージを高めようと、クラシックな街路灯を新設したり、縁台を店先に出して、ムード作りにつとめている。
植梅の浅井美恵子さん
(ドミール千駄木)
菊人形が一番盛んだったのは明治三十二〜七年頃、ちょうど日露戦争の頃ですね。
大正天皇が皇太子のころも見にいらしたそうですよ。十月の十日すぎから十一月末までやっていて、天長節(明治天皇誕生日)つまり今の文化の日前後が見頃というので一番人出が多かったといいます。
菊人形の小屋は坂下からヤブ下通りまでのほんの短いものですが、出店は今の向ヶ丘、郁文館のあたりまで続いていたそうで、白山の方からの客と谷中三崎坂の 方からの客がかち合って流れない、押すな押すなの盛況だったといいます。外人や偉い方は上野の西郷さんの下あたりから人力車でいらしたらしいですね。
はじめの頃はただで、知人や親戚に見せるようなものだったのが、人気が出て五厘とか一銭の木戸銭を取るようになってだんだん大仕掛になり、まわり舞台とか、その頃珍しかった蓄音機で役者のセリフを流したりしました。
大きいのは種半、植惣、植重、それにうちが植梅と四軒あって、お互いに出し物は秘密、だいたいその年の歌舞伎の当たり狂言で趣向をこらしました。
人形の胴体、着物は針金にわらを巻いたのに、根つきの菊を這わせるのです。期間が長いので毎朝の水やりやしおれた花の植えかえが大変です。それやこれやで 五〜六十人の人間が一軒の植木屋にいたそうですけど、どうやって暮らしてたんでしょう。家族は一番隅の部屋で食事したり休んだりしてたらしいですね。
でも大変な収入があったそうですよ。上がりをざるに入れ、樽に入れ、数える人も連れて日銀へ持ってったそうです。押入れにお金を入れとくと、何人も泥棒が入って刑事が来たりの大騒ぎ。舞台を回す人にまで大入袋が出たっていうから。
菊人形のふた月の収入で一年食べてゆくわけですから、雨が降らないことばかりを念じて、おじいちゃんは空ばかり見上げていたそうです。
清水清大園の清水喜代さん
(千駄木二丁目)
父が清大園という植木屋で、宮内庁に勤めて御所の盆栽のお世話などしていたのですが、菊人形のころは手助けしていたようです。いろんな芝居なんかの人形の着物の模様を赤や黄や白の小菊でこしらえていく。そりゃきれいなものでした。
私が見たのは明治四十四年の最後のころ、今の地下鉄の出口、坂の角のところに大きな歌舞伎十八番の暫の人形が飾ってあったわ。一番大きなのは、そこから少 し上がった今の荒物屋さんのあたりに植重というのがあって、十二段返しとか凄かった。上りをたてて呼び込みもとびかって、賑やかでしたね。坂は土の道で もっと狭くって、とても出店を出すどこじゃない。それぞれの店の奥に入るように見世物が作ってあったんです。
この辺も淋しいところで家は離れているし近所づきあいなんてなくて、フクロウや大木や竹ヤブでホントに怖かったわ。
天野きみさん
(菊見せんべい 明治八年創業)
団子坂の菊人形といっても、実際に見た方は少なくなりましたね。私もまだ小さかったものですから親に連れて行ってもらった記憶ぐらいで。お店も忙しいし、、間中に出かけたのは一〜二回くらい。
当時は遠くまで出かける楽しみもなかったせいか、やはりそりゃ嬉しくて。でも憶えているのは暗くてお化けでも出そうな感じ。小屋の中も薄暗くてよく見えないし、大きなお人形が菊の花や葉っぱをつけてぬっと立っているのが、気味悪いというのか、恐いだけでした。
染井鉱作さん
(千駄木四丁目)
ウチは太田道灌のお局で平田お染というのが祖先。祖父の代までは国学者で代々不憐庵と号していた。団子坂の菊人形では浅井、浅野、染井と大きな方だったけ ど、明治末に火が消えたようになってからは、呼び込みの連中は大方、活動の弁士になったね。徳川夢声なんかの師匠格の染井三郎なんてのも、ウチの呼び込み やってた男で屋号を芸名にしたのさ。
「その頃の団子坂附近は、坂の両側にこそ町家が並んでいましたが、裏通りは武家屋敷や寺や畑ばかりで、ふだんは田舎のように寂しい所でしたが、菊人形の繁 盛する時節だけは江戸中の人が押掛けて来るので大へんな混雑でした。それを当てこみに、臨時の休み茶屋や食い物店なども出来る。柿や栗や芒の木兎などの土 産物を売る店も出る。まったく平日とは大違いの繁昌でした。」(岡本綺堂「半七捕物帳」より 文久元年=一八六一頃)
藪そば遺聞
団子坂の途中、今のドミール千駄木から団子坂マンションのあたり、江戸時代から「藪そば」という有名なそば屋が菊人形の客を集めていた。千駄木山の中腹でのどかな田園風景が見下せ、庭も凝った作り。それを眺めながらのそば、そしてお酒ときたらもう止められない。
竹藪が多かったから藪そば。近所の人は菊そばともいったとか。この店は明治三十九年に廃業してしまった。それが、今全国に三千店もある藪そばの元祖だそうである。かの有名な神田の藪も、並木の藪も、上野の藪も、ここからのれん分けしたものだという。
九月上旬の東京新聞にそのことがでていて、団子坂の藪の創業者の墓前で慰霊祭が行なわれたとか。子孫も今はなく、全国の「藪そば」の店主たちは、この団子坂藪に関する情報を探しているそうだ。どなたかご存知の方があれば、私どもの編集室にご連絡ください。
菊というとまずイメージするのが、仏壇の花。長もちしていいのだが、他の花が枯れ、葉が黄色くなっても花だけはまだまだといった顔で咲き続ける。そんなのを植木鉢にでもさせば根付いてしまうこともある。なんと生命力のある花だろう。
昔、中国で菊の群生地の谷の水を飲んだ仙人が七百歳まで生きたという伝説も納得してしまいそう。
若い人には今ひとつ人気がない花だが探ってみると「キク」、なかなか奥が深そうだ。
渡来/醍醐天皇のころ、今から約千百年前に一般には中国から朝鮮を経て入ってきたといわれる。そのころ日本に野生の野菊はすでにあった。
分類/キク科の一年草または多年草で、学名Chrysantemun
花ことば/白は誠実・貞操。赤はあなたを愛する。黄は失恋。
菊の紋/皇室で菊の紋を使うようになったのは、後鳥羽天皇が始まりといわれているが、皇室が「十六葉八重表菊」皇族が「十四弁の裏菊」と決ったのは明治二年とわりに最近のこと。
記章/学校の記章には桜が多く使われているが、弁護士、国会議員、市区町村会議員のバッジは、ほとんどが菊を形どっている。
菊の被綿(きせわた)/陰暦の九月九日、中国では前夜に菊に綿をかぶせ、かおりとしずくをすいとらせて、それで体をぬぐうと長寿を得るという。
重陽の宴/平安時代、日本でもこれにあ やかり陰暦九月九日に菊を飾り、菊酒を天皇より賜って、長寿を保ち、わざわいを払う儀式が行なわれた。
薬用/漢方では、花を乾燥させ煎じて飲むとカゼの頭痛、めまいを治すとされまた、葉の生もみ汁は、おできや虫さされに効く。
菊酒/熱くした清酒一合に対し、十輪の食用菊をむしって入れ、すぐにふたをしてさます。長寿を保つ魔法の薬。
食用菊/さっとゆでる時には、酢を少し入れると色がさめずきれいにあがる。酢の物・あえ物・小菊の天ぷらなどの他に生でサラダにちらすのもきれい。少しかわったところでは、ファッチュという小菊を浮かした朝鮮風白玉団子もあるそうだ。
菊あわせ/九世紀、宇多天皇のころ盛んに行なわれた。持ちよった菊の色香、姿形を競い合う遊びで、負けると罰杯といって酒を強いられた。
菊人形/江戸初期より、菊の花葉を用いて人物・花鳥・動物などの形を細工するようになった。中山義秀の小説『厚物咲』は菊づくりの男の物語。
菊供養/菊の花一本を献花し、かわりにすでに観音さまに供えてあるものをもらいうける。陰干しにして枕の下に入れて寝ると、頭痛の心配がない。浅草寺で十月十八日に行われる。
まずは最盛期、明治二十年代の菊人形を描いた二葉亭四迷の『浮雲』。世渡りの下手な主人公文三は恋敵本田、恋人お勢の菊人形見物にも置いてけ堀を食う。
「さてまた団子坂の景況は、例の招牌(かんばん)から釣込む植木屋は家々の招きの旗幟(はた)を翩飜と金風(あきかぜ)に飄(ひるがえ)し、木戸々々で客 を呼ぶ声はかれこれからみ合て乱合て、入我我入(にゅうががにゅう)でメッチャラコ、唯逆上(ただのぼせあが)ッた木戸番の口だらけにした面(かお)が見 える而巳(のみ)で、何時見ても変ッた事もなし。」
さて下って明治四十一年の『三四郎』。
田舎から東京の大学に入った三四郎は憧れの 美禰子らと菊人形見物へ。
「右にも左にも、大きな葭簀掛の小屋を、狭い両側から高く構えたので、空さえ存外窮屈に見える。往来は暗くなる迄込み合っている。其中で木戸番が出来る丈大きな声を出す。「人間から出る声じゃない。菊人形から出る声だ」と広田先生が評した。」
その『三四郎』に示唆を受けて書かれたという森鴎外の『青年』は明治四十三年。この小説には根津や谷中もたっぷり登場。
「四辻を右へ坂を降りると右も左も菊細工の小屋である。国の芝居の木戸番のように、高い台の上に胡座(あぐら)をかいた、人買か巾着切りのような男が、ど の小屋の前にもいて、手に手に絵番付のようなものを持っているのを、往来の人に押し付けるようにして、うるさく見物を勧める。」
鴎外がこれを書いた翌々年の四十五年、団子坂菊人形は両国や浅草に押されて、廃業のやむなきにいたっている。
地域雑誌「谷中・根津・千駄木」
谷中墓地にリスがいるの知ってる?昔、根津に遊郭があったの知ってる?言問通りの田辺文魁堂の筆はピカソやミロが使ったんだって。朝倉彫塑館の池には、いまだに清水がこんこんと湧いているよ。そんな話題が満載。
「谷根千」は池の端、桜木、向丘、日暮里など周辺部も含め、この街に住む方々、いいお店、史跡、古い町並、年中行事などをテッテイ的に取材、ご紹介します。取材に行くから待っててね。
A5判48頁/季刊/二五〇円(年四冊
千円)/宅配もします。
「谷中スケッチブック」
私は動坂で生れ、小さい頃から、この静かで温かい谷中の街が大好きで、ずっと歩き回ってきました。でもこのところ、古い民家も次々と姿を消し、一夜にしてコンクリの駐車場になって、私は胸がドキン、キューンと高鳴るのです。
そこで今のうちでなければ、の思いと二人の子を抱いて谷中を取材しました。住んでいる者でなければわからない、谷中の四季の風と匂いと音と人情をたっぷり書き込んだガイドです。
森まゆみ著/十一月発行/発行エルコ
社/予価千二百円/宅配も可/予約
谷中・根津・千駄木の生活を記録する会
谷中・根津・千駄木は震災にも繊細にも耐えて残った町で、古くからのお寺、石仏、町並、暮らしぶり、人情がたくさんたくさん残っています。
それらをフィールド・ワーク(古老に聞いたり、街を歩いたり、地図を作ったり、事物を収集したり)で総合的に調査記録していきたいと思います。勉強しながらの楽しい作業ですよ。心も見も軽い若い方大歓迎。
当面は月一回の勉強会や調査をして、雑誌「谷中・根津・千駄木」で発表していきます。
菊まつり特集
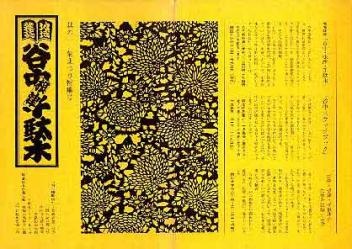
表紙
地域雑誌 谷中根津千駄木
その一 菊まつり特集号
”向う横町の”
笠森お仙子守唄
団子坂の菊人形
大円寺と瘡守稲荷
笠森お仙伝説
三崎坂イラストまっぷ
明治はるか菊人形
植梅の浅井さん他
文章に現れた菊人形
向う横町の
むこうよこちょのおいなりさんへ いっせんあげて
ちゃっとおがんでおせんの茶屋へ
こしをかけたらしぶ茶をだして
しぶ茶よこよこよこめでみたらば
こめのだんごか つちのだんごか おだんごだんご
このだんごをいぬにやろうか ねこにやろうか
とうとうとんびにさらわれた
笠森お仙に題を取ったこの歌は、昭和初期のころまで、東京を中心に関東・東北地方で広く歌われた。
笠森稲荷に願をかけるときは、まず土の団子を供え、願いが叶って願ほどきには、米の団子を供える慣わしだった。だから門前の茶店では、土と米と両方の団子を売り、茶屋の女たちは、「米のかえー、土のかえー」と声をかぎりに叫びたてていた。
団子坂の菊人形
団子坂とは地下鉄千代田線千駄木駅の出たところを本郷方面に上がってゆく坂である。古くからの道で汐見坂、千駄木坂、七面坂、菊見坂の別称もあるらしい。
団子坂の名は、団子茶屋があったからとの説もあるが、明治末にはもう一軒もなかった。急なためコロコロ団子のようにコケる人が続出したからとも、団子のよ うな小石があったとも。とにかく上り一町幅二間半と狭くて急で、しかもS字型に曲がって、上から来ると奈落の底に沈んでいくような心地がしたとか。
馬車や人力車で来てもたいてい、坂の上下で降りて歩き、そのための高下駄も用意されていた。なかには命しらずもいて、曲り角で車もろとも転がって大怪我を した話もある。そのショック除けに、S字の曲る角には木の柵がしてあったという。周りは森、下は田んぼ。今、ビルの立ち並ぶ坂からは想像もつかない眺めで ある。
この本郷台へ上る丘を千駄木山といった。坂上に森鴎外が、明治二十五年から大正十一年、死去するまで住んだ千朶山房があり、遠く品川の海を臨めるので、のち観潮楼と称した。今の区立鴎外記念本郷図書館である。
自雷也もがまも枯れたり団子坂(子規)
さて、いつのころからか染井、駒込から千駄木にかけては植木屋が多く、文化年間、巣鴨で菊人形をはじめ、それが大当りをとったのにあやかって、団子坂でも始まったのが安政三年(一八五六)という。
維新前の団子坂の貴重な資料として英人ロバート・フォーチュンの紀行文がある(『江戸と北京』一八六三)。
「この美しい土地は谷間にある。両側には木の茂った丘があり、峡谷から丘の際にかけて庭園や魚のいる池や茶屋がある。
・・・・この庭園で最も奇妙な眺めは、菊の花で作り上げた夫人の像【イミテーション・レディ】であった。そのために何千という花が用いられている」
初めて木戸銭(三文)を取って菊人形を見せたのは明治八年。これが大評判になって翌年には三十軒も店が出た。種半、植惣、植梅、植重、植浅、高木、薫風 園、花屋などが有名である。出し物は忠臣蔵、八犬伝、太閤記、曽我の仇討などの人気芝居がテーマ。首は人形師が人気俳優そっくりに作る。使うのは一度切り である。
人形の衣装の小菊はこの近辺では間に合わず、染井、巣鴨や王子あたりから取り寄せた。これを竹細工で編んだ胴に根つきのまま植えるが、ほぼ五日ごとに萎れ たのを取りかえるのと、水やりの作業で職人たちはクタクタだった。菊人形のほか、けんがいや大輪など、花壇菊もかざって見せていた。
明治十年ごろが一つのピークで、十五年ごろは団子坂が一手にひきうけ、二十年代が最盛期、日露戦争後はやや廃れ、明治四十二年、名古屋の黄花園が両国国技館に菊人形を開いたのに人気をさらわれ、四十五年、団子坂の菊人形は潰滅した。
大円寺と瘡守稲荷
団子坂下から谷中の方へ、柳通りと三崎の商店街を抜けて上がってゆく。すると左側、OBスタジオのクラシックなビルの隣りに大円寺はある。
高光山大円寺の創立は古く、天正十九年(一五九一)、家康が関東八ヵ国を秀吉から賜って、江戸に入城した翌年。その頃の江戸は字のごとく、葦がぼうぼうと生えた入江の沼地であった。
大円寺は大円院日授上人によってその年、神田加賀原に建立された。いまの医科歯科大のあたりである。もっとも上人が草庵を結び、日蓮像を安置したのは、それより以前の天文年間(一五三二〜五四)、いわゆる戦国の世のさなかである。
さて、徳川の世となって、江戸は首府になり、お城を中心に街づくりがすすめられると、神田は江戸の中心部で重要視され、神田にあった寺町は区画整理で郊外 に移された。天和二年(一六八二)のいわゆる「八百屋お七の火事」で類焼した大円寺は、上野寛永寺の清水門脇、今の清水坂(暗闇坂)の辺に移る。
さらに元禄十六年(一七〇三)の大地震と火事で、またまた大円寺は焼失。このとき現在地の谷中に移った。この火事で江戸の町の大半は倒壊、死者は四万と伝 えられる。このころ幕府の日蓮宗への弾圧が激しかったが、 大円寺は第六世日身上人が檀徒をまとめ、災難を乗り切っている。
そして大円寺に瘡守稲荷が遷座したのは享保十年(一七二五)五月十九日のこと。もともとは檀徒の白山の旗本、大前孫兵衛重職【しげもと】の邸にあった。彼 は自身、腫物【はれもの】に苦しみ、この病に霊験あらたかな摂津芥川(大阪府)の笠守様を、宝永年間に自邸に勧誘し、お祈りすると、たちまちにして癒っ た。その評判が江戸中に伝わり、人々が大前邸に押しかけて困るというので、大前氏が大円寺に移したものである。
それ以来、「谷中の瘡守様」は腫物(皮膚病)と腰から下の病に霊験あらたかというので、民間信仰の中でも特に参詣人が多かった。梅毒などに苦しむ吉原の女 郎たちも髪をしゃぐまに結い、歩いて急な三崎坂を下ってきた、とは「まつうら」酒店の松浦照子さんの記憶である。もっとも今は痔とかアトピーの平癒祈願が 多いそうだ
大円寺は紫陽花【あじさい】の美しい、しっとりとした寺である。が中に入ると本堂が二つ棟を合わせつながった不思議な形をしているのに気付く。右が薬王殿 で瘡守様を祀り、左は経王殿で祖師日蓮像を祀っている。つまり右は神式で左は仏式。こんなおもしろいスタイルの寺は東京広しといえどここだけである。これ は明治の神仏分離の危機を、瘡守稲荷(神)を薬王菩薩(仏)の形に変えて乗り切った。二十二世日★上人の苦心の表われである。
(インターネット版注 ★マークは言べんに甚の字です。パソコンではでないのでご勘弁を)
笠森お仙伝説
数々の工夫を凝らして錦絵を草創した鈴木春信と、彼のモデルで明和の美女と謳われた笠森お仙。これは春信の筆がたつのでお仙が有名になったのか、あまりにお仙が美しいので春信の絵が売れたのか、卵とニワトリみたいな関係にある。
この二人の碑が大円寺境内、本堂の向って右手に建てられたのは大正八年、春信の百五十回忌。春信の碑は笹川臨風お仙の碑は永井荷風の撰文によるもの。
笠森お仙はたしかに笠森稲荷の門前の茶屋に、江戸は明和のころいた美しい茶汲み女であるが、それは実は谷中の大円寺の瘡守稲荷ではなく、感応寺(いまの天 王寺)の子院福泉院にあった笠森稲荷なのだという。 三崎坂を上って菓子屋の角を左へ曲がり日暮里駅へ向かう途中右側に功徳林寺という寺があり、お仙のいた笠森稲荷があったのはここら辺り、大円寺の谷中瘡守 に対し、日暮里の笠森様という。
笠森お仙の美しさは、「ひとたび見れば人の足を駐【とど】む。再び見れば人腰を抜かす」(大田南畝)とまでいわれたぐらい。浅草観音奥山の楊子屋のいちょ う娘お藤と、天下の人気を二分したが、お藤が化粧の濃い人工的な美女であったのにくらべ、お仙は白粉に汚されることのないナチュラルな美女であった。
その天女が降り立ったような美しさを一目見ようと稲荷の門前はごった返し、お仙の姿は錦絵【プロマイド】、読み売り【しんぶん】のモデルとなり、手拭いに も染まり、和歌川柳にもうたわれ、ついにはお仙のような美人を生みたい親の願かけが始まる始末。 お仙が百姓娘だの、恋愛沙汰だの、怪死だのの巷説は、これに題材をとった芝居のフィクションである。有名な手まり唄は冊子の冒頭に掲げた。
本当のところ、お仙は茶屋鍵屋五兵衛の実の娘で、あんなにもてはやされたのに二〜三年で店から姿を消し、幕府お庭番の倉地政之助と結婚して久太郎ほか数人の子をなし、平和な一生を送っている。
しかし引退後もお仙は人の噂に上り、「とんだ茶釜が薬鑵缶に化ける」の言いまわしを流行らせた。お仙めあてに行ってみると、美女はいなくて、親父五兵衛の ハゲ頭しか見えなかったというわけ。引き際の見事さ、幸せな人妻ぶり、引退後の神格化という点で、明和の美女は、昭和の百恵ちゃんにそっくりだ。
春信とお仙の碑は場所こそ違え、感応寺と同じ日蓮宗の古刹大円寺に建っており、特にお仙の碑文はいかにも荷風らしい小粋なもの。
「女ならでは夜の明けぬ日の本の名物、五大州に知れ渡るもの、錦絵と吉原なり、笠森の茶屋かぎや阿仙、春信の錦絵に面影をとどめて百五十有余年、嬌名今に高し。今年都門の粋人春信が忌日を選びて、ここに阿仙の碑を建つ。時恰も大正己末夏鰹のうまひ頃」
さんさき坂マップ
三崎の地名の由来は古く鎌倉時代にさかのぼるという。
当時は不忍通りの低地は海で谷中、駒込、田端の三つの台地が岬となっていたことから、三崎の名が起こった。
三崎坂から団子坂へ、そして本郷へのルートは、五百年位前から開けた古道である。三崎坂はまたの名を首ふり坂。昔々どこの寺にか、首をふって歩くお坊様がいたからとか。
坂下のよみせ通りからへび道へとつながる通りには藍染川が流れ、びわ橋という橋がかかっていた。
今は文京区の柳通り商店街から、よみせ通りを渡って台東区のさんさき坂商店街に入る。
いわば谷中への入り口で、谷中散歩には日暮里駅からのルートも良いが、千代田線千駄木駅からのルートも便利。
商店街では「江戸のある町」のイメージを高めようと、クラシックな街路灯を新設したり、縁台を店先に出して、ムード作りにつとめている。
明治はるか菊人形
植梅の浅井美恵子さん
(ドミール千駄木)
菊人形が一番盛んだったのは明治三十二〜七年頃、ちょうど日露戦争の頃ですね。
大正天皇が皇太子のころも見にいらしたそうですよ。十月の十日すぎから十一月末までやっていて、天長節(明治天皇誕生日)つまり今の文化の日前後が見頃というので一番人出が多かったといいます。
菊人形の小屋は坂下からヤブ下通りまでのほんの短いものですが、出店は今の向ヶ丘、郁文館のあたりまで続いていたそうで、白山の方からの客と谷中三崎坂の 方からの客がかち合って流れない、押すな押すなの盛況だったといいます。外人や偉い方は上野の西郷さんの下あたりから人力車でいらしたらしいですね。
はじめの頃はただで、知人や親戚に見せるようなものだったのが、人気が出て五厘とか一銭の木戸銭を取るようになってだんだん大仕掛になり、まわり舞台とか、その頃珍しかった蓄音機で役者のセリフを流したりしました。
大きいのは種半、植惣、植重、それにうちが植梅と四軒あって、お互いに出し物は秘密、だいたいその年の歌舞伎の当たり狂言で趣向をこらしました。
人形の胴体、着物は針金にわらを巻いたのに、根つきの菊を這わせるのです。期間が長いので毎朝の水やりやしおれた花の植えかえが大変です。それやこれやで 五〜六十人の人間が一軒の植木屋にいたそうですけど、どうやって暮らしてたんでしょう。家族は一番隅の部屋で食事したり休んだりしてたらしいですね。
でも大変な収入があったそうですよ。上がりをざるに入れ、樽に入れ、数える人も連れて日銀へ持ってったそうです。押入れにお金を入れとくと、何人も泥棒が入って刑事が来たりの大騒ぎ。舞台を回す人にまで大入袋が出たっていうから。
菊人形のふた月の収入で一年食べてゆくわけですから、雨が降らないことばかりを念じて、おじいちゃんは空ばかり見上げていたそうです。
清水清大園の清水喜代さん
(千駄木二丁目)
父が清大園という植木屋で、宮内庁に勤めて御所の盆栽のお世話などしていたのですが、菊人形のころは手助けしていたようです。いろんな芝居なんかの人形の着物の模様を赤や黄や白の小菊でこしらえていく。そりゃきれいなものでした。
私が見たのは明治四十四年の最後のころ、今の地下鉄の出口、坂の角のところに大きな歌舞伎十八番の暫の人形が飾ってあったわ。一番大きなのは、そこから少 し上がった今の荒物屋さんのあたりに植重というのがあって、十二段返しとか凄かった。上りをたてて呼び込みもとびかって、賑やかでしたね。坂は土の道で もっと狭くって、とても出店を出すどこじゃない。それぞれの店の奥に入るように見世物が作ってあったんです。
この辺も淋しいところで家は離れているし近所づきあいなんてなくて、フクロウや大木や竹ヤブでホントに怖かったわ。
天野きみさん
(菊見せんべい 明治八年創業)
団子坂の菊人形といっても、実際に見た方は少なくなりましたね。私もまだ小さかったものですから親に連れて行ってもらった記憶ぐらいで。お店も忙しいし、、間中に出かけたのは一〜二回くらい。
当時は遠くまで出かける楽しみもなかったせいか、やはりそりゃ嬉しくて。でも憶えているのは暗くてお化けでも出そうな感じ。小屋の中も薄暗くてよく見えないし、大きなお人形が菊の花や葉っぱをつけてぬっと立っているのが、気味悪いというのか、恐いだけでした。
染井鉱作さん
(千駄木四丁目)
ウチは太田道灌のお局で平田お染というのが祖先。祖父の代までは国学者で代々不憐庵と号していた。団子坂の菊人形では浅井、浅野、染井と大きな方だったけ ど、明治末に火が消えたようになってからは、呼び込みの連中は大方、活動の弁士になったね。徳川夢声なんかの師匠格の染井三郎なんてのも、ウチの呼び込み やってた男で屋号を芸名にしたのさ。
「その頃の団子坂附近は、坂の両側にこそ町家が並んでいましたが、裏通りは武家屋敷や寺や畑ばかりで、ふだんは田舎のように寂しい所でしたが、菊人形の繁 盛する時節だけは江戸中の人が押掛けて来るので大へんな混雑でした。それを当てこみに、臨時の休み茶屋や食い物店なども出来る。柿や栗や芒の木兎などの土 産物を売る店も出る。まったく平日とは大違いの繁昌でした。」(岡本綺堂「半七捕物帳」より 文久元年=一八六一頃)
藪そば遺聞
団子坂の途中、今のドミール千駄木から団子坂マンションのあたり、江戸時代から「藪そば」という有名なそば屋が菊人形の客を集めていた。千駄木山の中腹でのどかな田園風景が見下せ、庭も凝った作り。それを眺めながらのそば、そしてお酒ときたらもう止められない。
竹藪が多かったから藪そば。近所の人は菊そばともいったとか。この店は明治三十九年に廃業してしまった。それが、今全国に三千店もある藪そばの元祖だそうである。かの有名な神田の藪も、並木の藪も、上野の藪も、ここからのれん分けしたものだという。
九月上旬の東京新聞にそのことがでていて、団子坂の藪の創業者の墓前で慰霊祭が行なわれたとか。子孫も今はなく、全国の「藪そば」の店主たちは、この団子坂藪に関する情報を探しているそうだ。どなたかご存知の方があれば、私どもの編集室にご連絡ください。
菊づくし
菊というとまずイメージするのが、仏壇の花。長もちしていいのだが、他の花が枯れ、葉が黄色くなっても花だけはまだまだといった顔で咲き続ける。そんなのを植木鉢にでもさせば根付いてしまうこともある。なんと生命力のある花だろう。
昔、中国で菊の群生地の谷の水を飲んだ仙人が七百歳まで生きたという伝説も納得してしまいそう。
若い人には今ひとつ人気がない花だが探ってみると「キク」、なかなか奥が深そうだ。
渡来/醍醐天皇のころ、今から約千百年前に一般には中国から朝鮮を経て入ってきたといわれる。そのころ日本に野生の野菊はすでにあった。
分類/キク科の一年草または多年草で、学名Chrysantemun
花ことば/白は誠実・貞操。赤はあなたを愛する。黄は失恋。
菊の紋/皇室で菊の紋を使うようになったのは、後鳥羽天皇が始まりといわれているが、皇室が「十六葉八重表菊」皇族が「十四弁の裏菊」と決ったのは明治二年とわりに最近のこと。
記章/学校の記章には桜が多く使われているが、弁護士、国会議員、市区町村会議員のバッジは、ほとんどが菊を形どっている。
菊の被綿(きせわた)/陰暦の九月九日、中国では前夜に菊に綿をかぶせ、かおりとしずくをすいとらせて、それで体をぬぐうと長寿を得るという。
重陽の宴/平安時代、日本でもこれにあ やかり陰暦九月九日に菊を飾り、菊酒を天皇より賜って、長寿を保ち、わざわいを払う儀式が行なわれた。
薬用/漢方では、花を乾燥させ煎じて飲むとカゼの頭痛、めまいを治すとされまた、葉の生もみ汁は、おできや虫さされに効く。
菊酒/熱くした清酒一合に対し、十輪の食用菊をむしって入れ、すぐにふたをしてさます。長寿を保つ魔法の薬。
食用菊/さっとゆでる時には、酢を少し入れると色がさめずきれいにあがる。酢の物・あえ物・小菊の天ぷらなどの他に生でサラダにちらすのもきれい。少しかわったところでは、ファッチュという小菊を浮かした朝鮮風白玉団子もあるそうだ。
菊あわせ/九世紀、宇多天皇のころ盛んに行なわれた。持ちよった菊の色香、姿形を競い合う遊びで、負けると罰杯といって酒を強いられた。
菊人形/江戸初期より、菊の花葉を用いて人物・花鳥・動物などの形を細工するようになった。中山義秀の小説『厚物咲』は菊づくりの男の物語。
菊供養/菊の花一本を献花し、かわりにすでに観音さまに供えてあるものをもらいうける。陰干しにして枕の下に入れて寝ると、頭痛の心配がない。浅草寺で十月十八日に行われる。
文学に現れた菊人形
まずは最盛期、明治二十年代の菊人形を描いた二葉亭四迷の『浮雲』。世渡りの下手な主人公文三は恋敵本田、恋人お勢の菊人形見物にも置いてけ堀を食う。
「さてまた団子坂の景況は、例の招牌(かんばん)から釣込む植木屋は家々の招きの旗幟(はた)を翩飜と金風(あきかぜ)に飄(ひるがえ)し、木戸々々で客 を呼ぶ声はかれこれからみ合て乱合て、入我我入(にゅうががにゅう)でメッチャラコ、唯逆上(ただのぼせあが)ッた木戸番の口だらけにした面(かお)が見 える而巳(のみ)で、何時見ても変ッた事もなし。」
さて下って明治四十一年の『三四郎』。
田舎から東京の大学に入った三四郎は憧れの 美禰子らと菊人形見物へ。
「右にも左にも、大きな葭簀掛の小屋を、狭い両側から高く構えたので、空さえ存外窮屈に見える。往来は暗くなる迄込み合っている。其中で木戸番が出来る丈大きな声を出す。「人間から出る声じゃない。菊人形から出る声だ」と広田先生が評した。」
その『三四郎』に示唆を受けて書かれたという森鴎外の『青年』は明治四十三年。この小説には根津や谷中もたっぷり登場。
「四辻を右へ坂を降りると右も左も菊細工の小屋である。国の芝居の木戸番のように、高い台の上に胡座(あぐら)をかいた、人買か巾着切りのような男が、ど の小屋の前にもいて、手に手に絵番付のようなものを持っているのを、往来の人に押し付けるようにして、うるさく見物を勧める。」
鴎外がこれを書いた翌々年の四十五年、団子坂菊人形は両国や浅草に押されて、廃業のやむなきにいたっている。
昭和五十九年十月十五日発行
編集人/森まゆみ 発行人/山崎範子 スタッフ/仰木ひろみ/鶴見 禎子
写植/今野早苗
印刷・製本・楠本タイプ印刷
編集室トライアングル
郵便番号一一三
文京区千駄木三−一−一−一〇二
(仰木方)電話 八二二−七六二三
特別定価百円
裏表紙(広告)
地域雑誌「谷中・根津・千駄木」
谷中墓地にリスがいるの知ってる?昔、根津に遊郭があったの知ってる?言問通りの田辺文魁堂の筆はピカソやミロが使ったんだって。朝倉彫塑館の池には、いまだに清水がこんこんと湧いているよ。そんな話題が満載。
「谷根千」は池の端、桜木、向丘、日暮里など周辺部も含め、この街に住む方々、いいお店、史跡、古い町並、年中行事などをテッテイ的に取材、ご紹介します。取材に行くから待っててね。
A5判48頁/季刊/二五〇円(年四冊
千円)/宅配もします。
「谷中スケッチブック」
私は動坂で生れ、小さい頃から、この静かで温かい谷中の街が大好きで、ずっと歩き回ってきました。でもこのところ、古い民家も次々と姿を消し、一夜にしてコンクリの駐車場になって、私は胸がドキン、キューンと高鳴るのです。
そこで今のうちでなければ、の思いと二人の子を抱いて谷中を取材しました。住んでいる者でなければわからない、谷中の四季の風と匂いと音と人情をたっぷり書き込んだガイドです。
森まゆみ著/十一月発行/発行エルコ
社/予価千二百円/宅配も可/予約
谷中・根津・千駄木の生活を記録する会
谷中・根津・千駄木は震災にも繊細にも耐えて残った町で、古くからのお寺、石仏、町並、暮らしぶり、人情がたくさんたくさん残っています。
それらをフィールド・ワーク(古老に聞いたり、街を歩いたり、地図を作ったり、事物を収集したり)で総合的に調査記録していきたいと思います。勉強しながらの楽しい作業ですよ。心も見も軽い若い方大歓迎。
当面は月一回の勉強会や調査をして、雑誌「谷中・根津・千駄木」で発表していきます。
本誌一号の訂正(谷根千其の二より)
3ページの中段隣→楼
8 上段恵美子さん→美恵子さん
明治天皇→大正天皇が皇太子の頃
9 下段千駄木三丁目→四丁目
11 昭和四十三年→明治四十三年
3ページの中段隣→楼
8 上段恵美子さん→美恵子さん
明治天皇→大正天皇が皇太子の頃
9 下段千駄木三丁目→四丁目
11 昭和四十三年→明治四十三年
